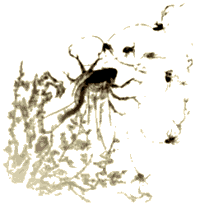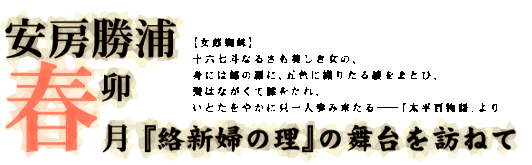隧道を抜けると、桜の薄紅と樹々の萌葱が有機的に混じり合う、観るも鮮やかな光景が眼前に拡がった。
隧道を抜けると、桜の薄紅と樹々の萌葱が有機的に混じり合う、観るも鮮やかな光景が眼前に拡がった。
一面の桜樹──とは違うが、これはこれで実に味わい深い景色である。
路はそのまま蒼蒼とした樹々の中を抜け岬へと続く。
申し訳程度に舗装された坂径は、まるで蜘蛛の巣がゆるゆると獲物の体力を奪い去る様に、
私の弛緩した躰を少しずつ鞭打つが、時折切れ間から美しい入り江の鳥瞰を望ませ、
獲物を更なる深みへと誘う飴を与える事も忘れない。
 此処、鵜原理想郷は、大正末期の鉄道大臣秘書後藤杉久青年に因って命名されたと聞く。
此処、鵜原理想郷は、大正末期の鉄道大臣秘書後藤杉久青年に因って命名されたと聞く。
また、別荘地として一躍脚光を浴びるようになったのも、同氏に因る大臣村建設に端を発する。
外房の荒波に因って削られた奇岩、鬱蒼と繁る老松、そして広大な海原と蒼穹が織り成す、
野趣溢れる景観は、京極氏に限らず、与謝野晶子や三島由紀夫など古くから幾多の文人に愛された名勝でもある。
山と海と空──万象がゆるやかに解け合う光景は確かに人を惹き付ける力を持っている。





いくつかの隧道と何処までもだらだらといいかげんに続く坂道を抜け、愚か者は進む。
人の手が僅かにしか及ばぬ山道は、決して来る者を優しく包む様な温いものでは無い。
しかし──だからこそ進む価値が有るのであろう。

 ふと何処からか視線を感じて立ち止まる。
ふと何処からか視線を感じて立ち止まる。
人影の無い薄暮の路は徐々にその濃度を深めてこそいるが、人外が跳梁するには少々早すぎる。
突如目の前を黒い影が横切り、がさりという音と共に叢へと消えた。
視ると、その暗がりには二つの小さな目が、脅えた光を宿して私を見つめていた。
仔猫である。
近付く私の足音に脅え、その小さな生き物は更に奥の暗闇へと消えた。
十年の歳を重ねた猫は化けると云うが、流石に彼にはまだ早い。
むしろ、三十年の歳を重ねた私の方が、彼の目には化け物として映るのだろう。





相変わらず路はだらだらと続き、惰丈に慣れた私の躰に鞭打つ。
途中幾度か町へと降る人々と擦れ違い、私の不安を打ち消した。
何の事はない。此処は観光地なのだ。

 ようやく登り坂が一段落し、眼前の木々の隙間から広大な海原が覗く。
ようやく登り坂が一段落し、眼前の木々の隙間から広大な海原が覗く。
彼方にて空へと溶ける碧海の美しさにほっと胸を撫で下ろすが、
己の進む路の先を見れば──又もやうんざりする程長い昇り坂が続いていた。

──呪いはあるぜ。しかも効く。
──呪いは祝いと同じことでもある。
──何の意味もない存在自体に意味を持たせ、価値を見出す言葉が呪いだ。
──プラスにする場合は祝うと云い、マイナスにする場合を呪うと云う。【姑獲鳥の夏】より
 更に進むと、沿道の樹々に桜が混じり始めた。
更に進むと、沿道の樹々に桜が混じり始めた。
雑木が鬱蒼と繁る路は作中の描写とは似ても似つかないが、それでも矢張り嬉しい。
思わず脚を止めて辺りを見回すと、幾つかの木々に何やら怪しげな物体が貼り付けられているのを見つけた。
──呪殺に使われるという厭魅──人形の類か!
──何者かが式を打った跡なのか!!
 ひとり興奮する私の思考は余所に、勿論それは斯様に物騒な代物などではなく、
鼠や茸を象った可愛らしい名札であった。近隣の小学生あたりが植樹した際にでも貼り付けたのであろう。
ひとり興奮する私の思考は余所に、勿論それは斯様に物騒な代物などではなく、
鼠や茸を象った可愛らしい名札であった。近隣の小学生あたりが植樹した際にでも貼り付けたのであろう。
しかし、これを式の形跡とするのもあながち間違いでは無い。
『姑獲鳥の夏』で中禅寺が語る様に、呪いも祝いも、その方向性は違えど本質は同じである。
或る者はその呪具に負の思いを込めて人を呪うが、この少女達は清らかな思いを込めて木々の成長を祝った。
その想いが届き、いつしか此処が満開の桜に包まれる事を──切に願う。





















 其処は最早、路と言える程の体裁すら留めて居らず、単に踏み固められた形跡の有る坂でしか無かった。
所々に散在するぬかるみに足を取られ乍らもなんとか進む。
其処は最早、路と言える程の体裁すら留めて居らず、単に踏み固められた形跡の有る坂でしか無かった。
所々に散在するぬかるみに足を取られ乍らもなんとか進む。
──当然、手摺りなど無い。
そして、漸く坂を登り切った時──突如、背中に寒気が走った。
それは描写上の演出でも無ければ、大袈裟な物言いでも無い。
あの瞬間、俯き気味に坂を登る私は、まるで背中に冷水を掛けられたかの様に
ぞーっと膚が総毛立つ寒気を、明瞭りと感じたのだ。
眼を上げると――其処には小振りな朱い鳥居が静かに佇んでいた。
 あれは恐怖では無い。
あれは恐怖では無い。
云わばあの感覚は"畏怖"である。
流石にこの時代に生きる人間として、私とて幽霊や妖怪の実在等は信じていない。
それは、神や仏といった超越者に関しても同様である。
だがあの時、私は明瞭りと理解した。
この世に人間を遙かに凌駕した力を持つ神なぞ「居ない」。
だが――人間を遙かに凌駕した力を持つ神は確かに「在る」のだと。
 中世の錬金術が西洋科学へと変貌し、世界の体系を次々と解明して行く中で、
人はいつしか科学の持つ本来の役割を忘れた。
中世の錬金術が西洋科学へと変貌し、世界の体系を次々と解明して行く中で、
人はいつしか科学の持つ本来の役割を忘れた。
科学には、飽くまでこの世界に元より存在する"理"を分類、体系化する事しか出来ない。
水が高きから低きに流れるのは何故だと問われれば、多くの人は「地球に重力や引力が働いているからだ」と答えるだろう。
では重力とは、引力とは何だ。
何故その力があると、物体を引き寄せる事が出来るのだ。
水素と酸素が化合するとどうなるかと問われれば、多くの人は「水が出来る」と答えるだろう。
では何故水素と酸素が化合すると水になるのだ。
何故異なる組成の物質が接触しただけで、構成元素の組み替えが起きるのだ。
科学の力ではそれを説明する事は出来ないし、また本来それを説明する必要も無い。
その部分は元から科学の担うべき役割ではないのだから。
だが別の言語体系を使う事で、それはいとも容易く説明する事が出来る。
そう、その力が――
この世界を構成する"理"と呼ばれる力こそが――"神"なのだと。







|